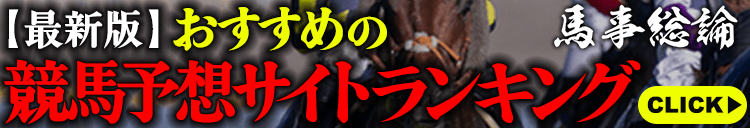有馬記念の歴史

有馬記念は中央競馬で行なわれる重賞競走(GI)で、千葉県船橋市に立地する中山競馬場で行なわれる人気の高いレースなのですが、どのようなルーツで開催されるようになったのでしょうか。
有馬記念のルーツとなるのはかつて中山競馬場で実施されていた中山大障害と呼ばれる障害競走です。
この障害競走はイギリスで人気の高いグランドナショナルの障害競走に倣ったもので、1932年から開催されている日本ダービー(東京優駿)に対抗する名物競技に育てるために1934年から開始され、当初は春と秋の年2回に行なわれていました。
障害として大竹柵や大生垣が設置され競走馬は飛越して乗り越え、ダートコースから芝コースと進む事になるのですが、大々的に開催される日本ダービーと比較をすると華やかさの面でどうしても劣る事になり、長く悩みの種とされていました。
そこで1955年当時の日本中央競馬会の2代目理事長であった有馬頼寧(ありまよりやす)の提案により中山グランプリと名称を変えて、新たなレースとして登場します。
この中山グランプリはこれまでの競技とは大きく異なり、ファン投票が実施されどの競争馬が出場するか決定する方式になり、ファンから好評を博して一気に人気を獲得します。
しかし第1回競技から程なく提案者である有馬頼寧が逝去し、これまでの功績から有馬記念に改称する事になり、名称のルーツは提案者の名前にあるのです。
現在行なわれている有馬記念は年に1回12月下旬に開催されており、年末の風物詩として定着しています。
競走条件はサラ系の3歳以上で出走が可能な頭数は最大16頭に及び、ファン投票が行なわれ上位10頭までが出場する事ができ、それとは別に外国馬に関しては優先的に出走することができます。
また2015年現在の賞金については高額に設定され、ジャパンカップについで高い1等賞金は2億5000万円とされています。
さらに天皇賞(秋)やジャパンカップなどを含め同一年内に全て優勝した場合は褒賞金・特別出走奨励金として2億円を交付されることになり、こうした点も大きな特徴です。